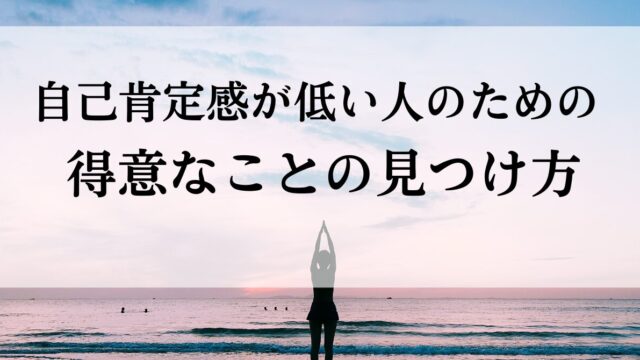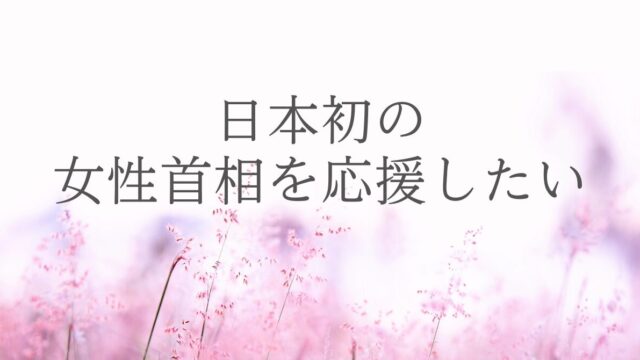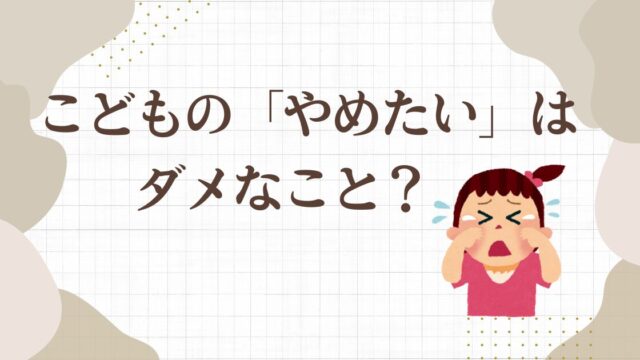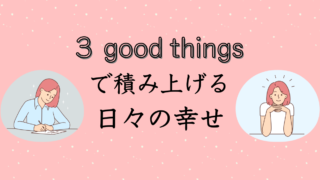先日、息子が来年入学する予定の公立小学校の就学時健診に行ってきました。
そこで感じた時代の変化などについて触れてみたいと思います。
1学年1クラスで問題なこと
我が家が住んでいる自治体でも、少子高齢社会を迎えています。
クラスの数は1学年1クラスがデフォルト。
息子が入学する予定の小学校も新1年性は1クラスのようです。
これは私たちが住んでいる地域が極端に少ないのではなく、どこの小学校区もだいたい1クラス、多くても2クラスが現状です。
近隣の小学校数校で統合の話も出ていますが、ひとまずは地域の小学校に入学し、中学年時にどこかの小学校と統合予定です。
就学時健診もだいたい20名くらいの保護者とその子どもたちが参加していましたので、確かにこれで一学年と考えると少ないよな、、、と感じました。
少ないことによる問題の1つとして、人間関係の硬直化が挙げられます。
いじめが起きた場合、逃げ場が少ないことは幼い子どもにとっては大きな問題となるでしょう。
人数が多いからといって、いじめが起きないわけではないですが、人数が増えればその分、人間関係も広がるし他の友人関係の可能性も広がりますよね。
少ないからこそのメリットも
子どもが少ない現状は今すぐ解決はできませんが、少ないからこそのメリットもあります。
例えば、わからない問題が出てきたときに、先生にじっくり質問することができるのではないでしょうか。
一人ひとりの友達と深く付き合うこともできたり、委員会活動やクラブ活動などで役割を持てる可能性も上がります。
これが人数が多い場合だと、先生も多くの児童の対応に追われ子どもと向き合えなかったり、児童数が多いがためにやりたいものがやれなかったりする可能性も高くなります。
人数が少ない、、、!と嘆くばかりでなく、こうしたメリットにも目を向けてみると、少人数ならではの良さも見えてきます。
親としてできること
息子が入学する予定の小学校に、今の園の友達で入学する予定の子は一人もいません。
少し離れた地域の園に入園させてしまったためなのですが(ちゃんと入園させたいと思った理由がある)、これも仕方のないことだと受け入れています。
人数が少ない中で、友達が一人もいないのは可哀想かな、、、とも思ったのですが、これからの長ーい人生の中で、知り合いが一人もいないという状況は多数発生してきます。
なんでもかんでも親が環境を整えてあげることがいいことだとも思わないし、子どもの順応性の高さに期待して、新しい環境でも楽しく過ごしてほしいです。
親としてできることは、家でのサポートと、どんなときも味方でいてあげることかと思います。
それに、小学校だけが全てではないし、小学校で学ぶことだけが大切なわけでもありません。
家庭で学べること、家族だからできること、そういったことも小学校に入ってからも取り組んでいきたいですね。
さいごに
小学校入学を控え、親としても不安なこともありますが、それよりも子どもと一緒にワクワクと期待感を持って準備をしていきたいと思いました。
いろんなことが待っているけれど、きっと楽しいから。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。